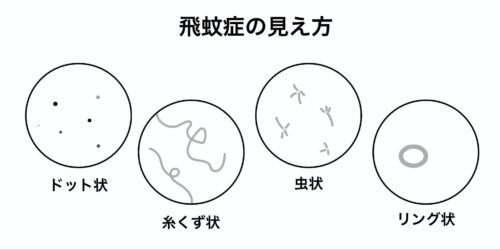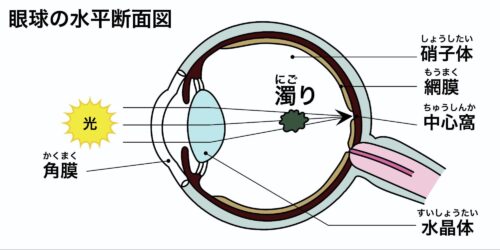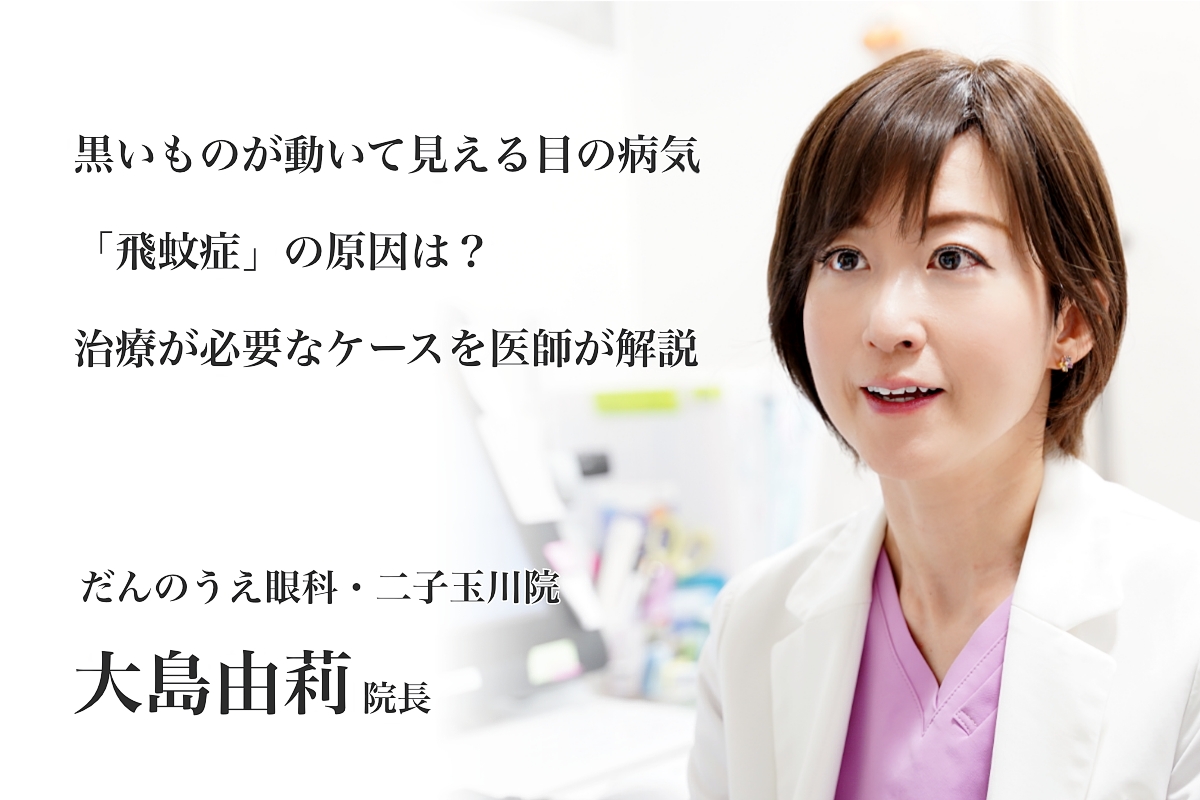「最近片目だけ涙が出る」「涙が溢れてティッシュやハンカチが手放せない」という悩みをお持ちではありませんか?
特に原因が分からないと、目の病気ではないかと不安になってしまうこともあるでしょう。
この記事では片目だけ涙が出る人に向けて、症状の原因や対処法を紹介します。
片目だけ涙が出る原因【目の病気】
片目だけ涙が出る症状には、目の病気が原因となっているものがいくつかあります。
その病気も涙が溢れやすくなるものから、炎症を伴うものまでさまざま。
似た症状も多いため判断が難しいですが、それぞれの特徴を理解するだけでも対処しやすくなるので、ぜひ覚えておきましょう。
細菌性結膜炎
細菌性結膜炎とは黄色ブドウ球菌や肺炎球菌などの、皮膚や粘膜にも存在する身近な細菌に感染することで起こる結膜炎です。
症状は主に、粘り気のある目やにが出る、白目部分が充血する、異物感、流涙症(涙が溢れること)など。
片側にだけ発症する場合もあるため、片目だけ涙が出る以外に、涙が出るほうに目やにや充血がある場合は、この細菌性結膜炎の可能性があります。
ストレスで免疫機能が低下していたり、目に小さな傷があったりすると、発症リスクが高まるのもこの病気の特徴です。
アレルギー性結膜炎
アレルギーを引き起こす原因物質が、結膜に入ることで起こるのがアレルギー性結膜炎。
原因となる主な異物はハウスダストやダニ、花粉といった定番のアレルゲンで、発症すると粘り気のある目やにや異物感、流涙症などの症状が出ます。
両目はもちろん、なかには片側にだけ発症するケースもあります。
特に花粉症が出る季節に片目だけ涙が出ると感じる、自宅にいるときだけ片側から出るのであれば、この病気の可能性があるといえるでしょう。
ウイルス性結膜炎
ウイルス性結膜炎は、目やにや涙の量が増える、まぶたが腫れる、充血などの症状が特徴の結膜炎です。
アデノウイルスが原因のはやり目が有名で、ほかにもヘルペスウイルスやエンテロウイルスが原因となっているタイプもあります。
片目だけに発症するケースが多い病気ですが、感染力が強いため対策や治療を進めないともう片方の目にうつる可能性も。
また、他の人にうつしてしまうリスクもあるので、ただの結膜炎と侮らず、気になる症状があった場合は早めに眼科を受診しましょう。
鼻涙管狭窄・鼻涙管閉塞
涙が目に溜まりやすくなることで涙目になる「導涙性流涙」を引き起こすのが、鼻涙管狭窄や鼻涙管閉塞です。
この病気は涙を排出するための穴である「涙点」から、その先にある「鼻涙管」までが副鼻腔炎や風邪による炎症、手術の後遺症などで塞がってしまうために起こります。
泣いているわけでもないのに、行き場をなくした涙が自然と目に溜まり、涙目になってしまうことが特徴。
ひどい場合には、ハンカチやティッシュなどが手放せなくなってしまいます。
涙の量は変わらないのに片目だけ涙が出る場合は、鼻涙管が塞がっている可能性もあるでしょう。
先天鼻涙管閉塞
先天鼻涙管閉塞とは、先天的な要因により起こる鼻涙管閉塞。
赤ちゃんの涙目の原因としても有名なもので、涙道が未発達な状態で生まれたために起こるといわれています。
1歳までに9割以上が自然に治るため、赤ちゃんに片目だけ涙が出る、両目が涙目になっているなどの症状があっても、あまり気にする必要はないでしょう。
しかし、まれに1歳を過ぎても治らない、定期的なケアが必要になる場合もあるので、気になるようであれば眼科で検査や治療を受けるのがおすすめです。
涙嚢炎
涙嚢炎とは、細菌感染によって涙道内にある「涙嚢」が炎症を起こす病気です。
雑菌の入った涙が涙嚢にたまることにより起こる病気で、鼻涙管閉塞症の患者や鼻涙管が狭い人が発症しやすいといわれています。
初期症状は両目、もしくは片目だけ涙が出る、目やにの量が増えるといった軽めの症状が中心。
しかし、炎症が進行すると化膿して目の周囲が腫れてしまうこともあるため、涙が出る症状に加え、目頭の周辺が腫れているなら早めに眼科を受診しましょう。
片目だけ涙が出る原因【その他】

片目だけ涙が出るという症状を引き起こすものは、目の病気だけではありません。
現代人ならではの症状や神経関連の病気といったものでも、このような症状がでる場合もあるのです。
次は、目の病気以外で片目だけ涙が出る原因となるものを紹介します。
ドライアイ
片目だけ涙が出る原因となりうる症状がドライアイ。
ドライアイとは、涙の量や質の低下により目が乾燥しやすくなる症状で、片目だけに発症することもあります。
症状は目の乾きや異物感が中心で、パソコンを長時間使用したときや、冷たい風に当たったときなどに涙が止まらなくなるといった症状が出るケースもあります。
片目だけ涙が出る症状のみであることは少ないですが、日頃から目の異物感や乾燥を感じているならドライアイが影響している可能性もあるでしょう。
逆まつげ
片目だけ涙が出る原因の1つが、まつげが目に当たりやすい状態になってしまう逆まつげです。
特に生まれつきまつげが内側に向いている、炎症性の病気や加齢によりまつげが不揃いに生えている、という場合は逆まつげが原因となっている可能性が高いでしょう。
重大な病気や感染症ではないため放置されがちですが、保険の範囲内で治療できることもあるので、症状が気になる場合は気軽に眼科を受診してみてはいかがでしょうか。
ストレス
実はストレスも片目だけ涙が出る症状を引き起こす可能性があるものです。
直接的な原因にはなりませんが、過度なストレスにより自律神経のバランスが乱れ、副交感神経が優位になりすぎてしまうと涙が止まらなくなる場合があります。
また、ストレス過多により免疫力が下がると、片目だけ涙が出る症状を併発するアレルギー性結膜炎や細菌性結膜炎にかかってしまうことも。
炎症のような目立った症状が少ないため判断は難しいですが、普段から不調を感じているならストレスが原因であることも十分に考えられます。
ゴミやホコリなどの異物
自分の部屋や屋外だけなどの限られた場所で、片目だけ涙が出るという場合にはゴミやホコリ、花粉などの異物が原因となっている場合もあります。
環境に関係なく片目だけ涙が出るなら他の原因が考えられますが、ホコリや花粉の多い環境でよく出るならこの異物を疑ってみましょう。
また小さなガラス片や鉄くず、木くずなどが目に入った場合は要注意。
目の表面に刺さるだけでなく角膜を傷つける可能性もあるので、この場合は早めに眼科を受診しましょう。
筋肉のこわばり
神経内科や眼科などを受診しても異常がない場合は、首まわりの筋肉のこわばりが原因とも考えられます。
メカニズムとしてはパソコンやスマホの使いすぎによる疲労で、眉の周りやこめかみ、首筋周辺の筋肉が緊張し、関連症状として片目の涙目が引き起こされることがあるのです。
他の原因と比べるとやや確率は低めですが、コリのような痛みがある場合は筋肉のこわばりもチェックしてみると良いでしょう。
顔面神経麻痺
顔面神経麻痺は顔の筋肉を支配する神経に異常が起き、麻痺が発生する症状です。
主な症状は、口角や頬がたれ下がる、まぶたが完全に閉じなくなるなど。
涙に関する神経にまで異常が出た場合は、涙の量が増える・減るといった症状がでることもあります。
まぶたが完全に閉じなくなった場合は「導涙性流類」、涙の量が増えすぎた場合には排出が間に合わない「分泌性流涙」と2パターンの流涙が起こりうるのも特徴です。
進行するとより麻痺がひどくなることもあるので、片目だけ涙が出る以外にも麻痺の症状がある場合は早めに眼科を受診しましょう。
抗がん剤の副作用
抗がん剤の副作用も、片目だけ涙が出るという症状を引き起こす原因の1つ。
どの抗がん剤でも起こりえますが、特に胃がんや大腸がんに使われる「TS-1(S-1)」の報告が多いといわれています。
この副作用は、細胞の増殖を抑える成分が涙に含まれてしまうことで起こるもので、人によっては涙の排出が難しくなる涙道閉塞を発症してしまうことも。
早期に発見すれば副作用に対する治療も簡単になるので、抗がん剤を飲んでいて片目だけ涙が出るならすぐに眼科医に相談するのがおすすめです。
コンタクト
コンタクトの不適切な使用も、片目だけ涙が出る症状を引き起こす原因です。
不適切な使用とは「付け方が間違っている」「管理や洗浄方法が不十分」「付けたまま目薬をさす」「長時間の使用」など。
このような使い方を続けてしまうと角膜が傷つき、流涙が起こるリスクが高くなってしまいます。
また、洗浄不足に関しては、アレルギー性の症状を誘発する可能性も。
説明書通りに使っていればトラブルは起きにくいですが、意識せずに使っていて片目だけ涙が出る場合は使い方を見直してみましょう。
群発頭痛
群発頭痛とは頭の片方、特に目の奥部分に激痛を感じる頭痛です。
片側に起こるのは偏頭痛と似ていますが、こちらは痛みが強く、夜~明け方に起こりやすいという特徴があります。
また、鼻水や涙が止まらなくなるといった症状もあるため、片目だけ涙が出る症状が激しい頭痛とともに現れる場合は、群発頭痛の可能性もあるでしょう。
治療や検査に関しては脳や神経に関する症状のため、脳神経外科や神経内科を受診するのが基本です。
片目だけ涙が出るときの対処法や治し方
片目だけ涙が出る原因の次は、対処法や治し方をチェックしていきましょう。
原因ごとに対処法が違うため判断が難しい部分もありますが、症状にマッチした対処法や治療法を選べば、症状の緩和や改善も期待できます。
目薬を使う
軽い炎症や軽度のアレルギー性結膜炎により片目だけ涙が出るなら、目薬を使って対処するのがおすすめです。
炎症により涙がでるなら抗炎症作用のある「プラノプロフェン」を含むもの。
アレルギー性結膜炎なら、抗アレルギー剤や抗ヒスタミン剤が配合された目薬を選ぶと改善が期待できます。
もしどれを使えば良いか分からない場合は、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。
部屋にアレルゲンを持ち込まない
アレルギー物質が原因で片目から涙が出る場合は、まず部屋にアレルゲンを持ち込まないように意識しましょう。
ハウスダストや花粉を完全にシャットアウトするのは難しいですが、量を減らすだけでも症状の緩和が期待できます。
花粉症であれば、花粉の時期に「洗濯物は外干しを控える」「窓を開けるのを控える」「家に入る前に花粉を落とす」などの対策が効果的。
ハウスダストやカビ、ダニであれば、こまめに掃除機をかけたり、空気清浄機を使ったりするのがおすすめです。
菌・ウイルスへの感染予防をする
ドライアイにより目のバリア機能が低下していたり、片目だけ結膜炎や涙嚢炎にかかっていたりする場合は、菌・ウイルスへの対策も重要です。
具体的には目をこすらないようにする、帰宅後の手洗いを徹底すること。
すでに病気が発症しているなら、家族と別々のタオルを使うのも効果的です。
特に前者の対策は風邪の予防にも役立つので、ぜひ気軽に実践してみましょう。
コンタクトの使い方を見直す
コンタクトが原因で片目だけ涙がでるなら、コンタクトの使い方を見直すのがおすすめです。
説明書の内容や医師の指示をしっかり守るのはもちろん、ケースも定期的に洗浄・除菌する、レンズを扱うときは石鹸で手を洗うことを徹底するとより安全に使えるでしょう。
メイクをする方であれば「コンタクトをつけてからメイクする」「落とすのはコンタクトを外してから」の2点を意識すると目に関するトラブルを減らせます。
また、花粉にアレルギーがあるなら花粉の時期のみメガネを使って、感染症のリスクを抑えましょう。
眼科を受診する
対策を実践したけれど改善しない、目の病気の疑いがあるならすぐに眼科を受診しましょう。
眼科であればしっかりと検査してくれるだけでなく、専用の目薬を使った点眼治療なども受けられます。
また、鼻涙管閉塞のような自分でケアできない症状も涙管チューブ挿入術や涙嚢鼻腔吻合術などの「涙道手術」で解消してくれます。
コンタクト関連のトラブルやドライアイなどにも対応してくれるので、症状が気になるなら気軽に受診してみましょう。
群発頭痛が疑われる場合は、脳神経外科や神経内科のほうがスムーズに対応してくれるので、眼科よりも先にこれらの科を受診するのがおすすめです。
なぜ片目だけ涙が出るかわからない場合は眼科へ行こう

原因をチェックしても何故片目だけ涙が出るかわからない、うまく原因を絞れない場合は、眼科を受診しましょう。
専門的な検査をしてくれるのはもちろん、経過の確認や治療もしっかりと進めてくれるので症状の改善も十分に期待できます。
また、ドライアイで片目だけ涙が出る方にはほうれん草や小松菜、ケールに多く含まれる「ルテイン」を意識的に摂るのもおすすめです。
優れた抗酸化作用により、ドライアイが進行する原因ともなる目の老化をしっかりとケアしてくれるでしょう。
忙しくて野菜を摂るのが難しいなら、ゼリーサプリ「朝のルテイン」を使ってみるのもおすすめ。
こちらは高品質で吸収効率にも優れたルテインが豊富に含まれているので、野菜不足が気になる方でも手軽にルテインを摂取できます。
美味しくて続けやすい、マンゴー風味仕立てになっているのもポイント。
手軽にルテインを摂って目の健康維持に役立てたい方は、毎日の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。